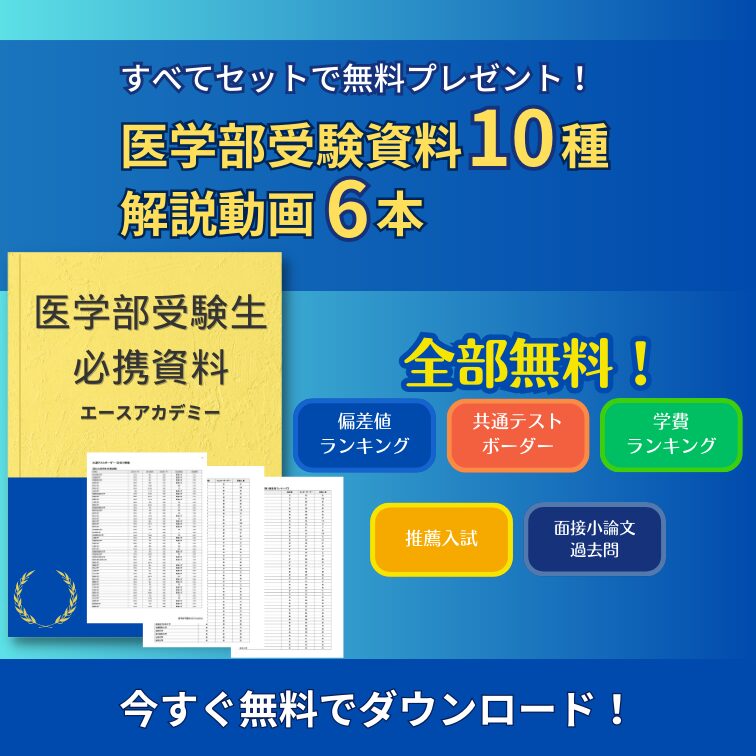<解説動画>
受験校選びは合格可能性に大きく影響する
医学部受験において、正しく受験校を選ぶことは非常に大切です。
成績を伸ばすことはもちろん大切ですが、受験校の選び方によっても合格可能性は大きく左右されます。
運営する医学部専門予備校では、生徒個別で受験推奨校を作成しています。
実際の指導経験やデータを基に、受験校選びのポイントと、よくある間違いを紹介していきます。
国公立医学部の場合
共通テストの結果が最重要!
国公立大学医学部の場合、出願校を決めるのは共通テストの後がおすすめです。
大学ごとにセンター(共通テスト)ボーダーや、共通テストと学科試験の配点比は異なります。共通テストの結果を基に、合格可能性がより高い大学を選びましょう。
共通テストが終わったらまずは自己採点を行ってください。
(共通テストの点数は合否に大きく影響するため、正確に自己採点を行いましょう。)
大学ごとの傾斜配点を算出し、センターリサーチのボーダーを踏まえた上でより有利な受験校を選んでいきます。
*傾斜配点とは、科目ごとの配点比から算出した点数です。
大学によって科目ごとの配点は異なり、英語の配点が大きくなる大学や、国語社会の配点が低い大学などがあります。
共通テストからリスニングの配点が大学によって変わるので注意しましょう。
共通テストからでも過去問演習は間に合う?
共通テストが終わってからでも、過去問演習は間に合います。
過去問演習を繰り返せば実力がつく訳ではありません。
私立医学部の受験が終わってから2-3回演習し、出題形式に慣れておくことで十分対応可能です。
大学によっては、共通テストの点数次第で合格がかなり厳しくなる場合があります。
共通テスト前に過去問演習を行う場合は注意しましょう。
私立医学部の場合
私立医学部は学費と難易度が反比例する
私立医学部は、学費と合格難易度が反比例する傾向にあります。
学費が安いほど難しく、高くなるほど易しくなるということです。
このような背景から、「どの学費帯の大学まで通えるのか」を決めておくことが非常に大切になります。
奨学金や学費については、受験生本人だけでなく、親御さんの協力が必要になります。早めの時期に話し合っておくことがおすすめです。
よくない例としては、「もともと国立専願だったけれど、受験直前になって私立の受験も検討しだす」というものです。
受験直前期に、学費の検討や家族との話し合い、願書の準備や急な過去問演習をすることとなり、受験生にとって大きなストレスとなります。
私立医学部は国公立大学医学部と異なり併願できるため、出願する大学の幅を広げることで合格可能性が上げることができます。
よくある勘違いと間違った出願方法
①「倍率が高い=難易度が高い」と考える
倍率が高い大学ほど難易度が高いと考え、出願を避けてしまうのは推奨できません。
倍率の高さは合格難易度にほぼ全く関与しないと考えて良いでしょう。
合格難易度の指標には、偏差値ランキングを活用するのがおすすめです。
②過去問の傾向、問題の難易度で選ぶ
「過去問研究を行い、出題されている問題の難易度で受験校を選ぶ」というのはよくある選び方ではあるものの、注意が必要です。
数学の難易度で考えてみましょう。
単科医科大学である浜松医科大学や福島県立医科大学は、数学の難易度が非常に高いことで有名です。
一方、総合大学である千葉大学や筑波大学の出題はオーソドックスなので「解きやすい」と感じる受験生は多いと思います。
しかし、偏差値ランキングを見ていただければ分かる通り、合格難易度自体は千葉大学や筑波大学の方が高くなります。
「問題の難易度」よりも「受験者層のレベル」が重要ですので、過去問の傾向だけを基準にするのはやめましょう。
実際、当塾の卒業生で、数学が苦手(偏差値55程度)な受験生が浜松医科大学に合格した例があります。
本番の入試では、手ごたえが20点程度だったようですが、センター試験や他教科でしっかり得点したことで、私立医学部含め合格されました。
*似たような話では、「科目ごとの配点」で決めるのもおすすめできません。
順天堂大学は数学の配点が低い(500点中100点)ですが、「数学が苦手な受験生」に必ずしもおすすめできる訳ではない、ということです。
(偏差値が70あるので受験層のレベルが高く、合格難易度自体が高いため。)
受験校を選ぶ時の注意点まとめ
ポイント①:問題の難易度よりも受験層のレベルを考える
問題の難易度や配点よりも、周りの受験層のレベルが合格難易度に影響します。
問題の難易度や配点を最優先に考えてしまうと、間違った受験校を選んでしまう恐れがあるので気を付けましょう。
ポイント②:問題の合うor合わないはアテにしない方がよい
問題の合う、合わないの正体は、大抵が「問題の難易度、出題形式がオーソドックスかどうか、試験時間に対して問題の分量が多いか」等です。
「解きにくい」と感じる問題は、他の受験生にとっても解きにくいことが多いですし、「解きやすい」と感じる問題は、他の受験生も同じように感じています。
問題の相性の重要度はあまり高くないので、受験校選びにおいては参考程度に留めるのがおすすめです。
国家試験合格率や大学の特徴も考慮すべき?
受験校を選ぶ段階で、国家試験合格率や大学の特徴、卒業後の進路などを考えるのは推奨していません。
受験校を選ぶ際は、「合格可能性を高めること」を最優先に考えて、国家試験の合格率や大学の特徴などは合格してから考えるのがおすすめです。
そもそも、出願した大学に、希望通りor予想通りの合格の仕方をすることの方が少ないです。
受験する前に迷うのは選択肢が多く時間がかかる上、蓋を空けると悩む必要はないケースもあります。
合格した医学部から、比較検討した上で選ぶようにしましょう。通常は、合格してからでも悩む時間は十分にあります。