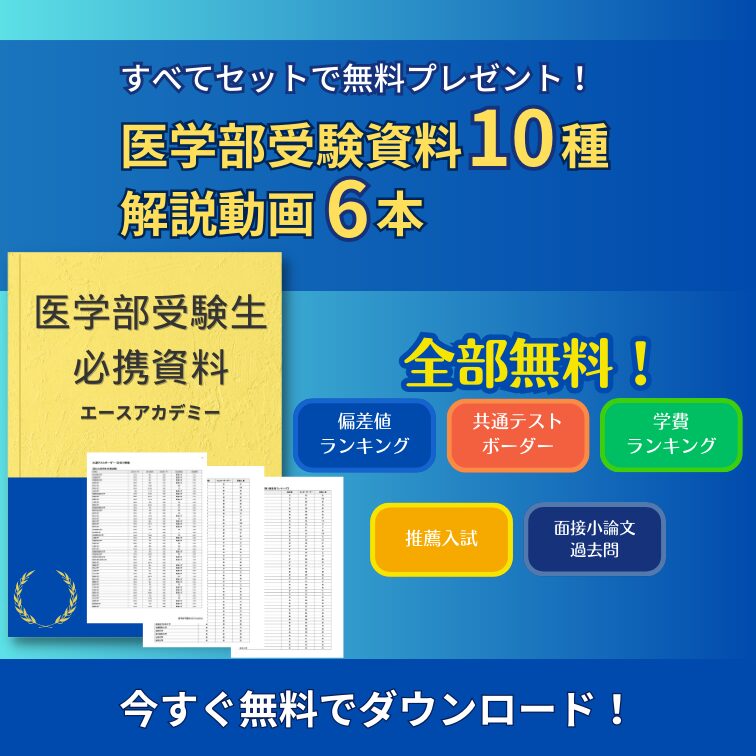<解説動画>
毎年生徒さんから受ける相談の1つに、地域枠の医学部受験に関する相談があります。
医療制度の現状を踏まえて、地域枠入試のデメリットについて解説しました。
地域枠入試を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
地域枠とは
地域枠入試とは、地域医療従事に意欲的な志願者を対象とした入試制度です。
地域枠では、卒業後の縛りがあります。
例えば、
・卒後9年間特定の地域あるいは特定の診療科で働く。
・卒後9年間を特定の地域あるいは診療科で働けば、学生時代の奨学金は返却免除になる。
というものです。
地域枠受験のメリット
地域枠受験は、各都道府県が設定しており、地域の医師不足を解消するため、指定する医療機関あるいは科(産婦人科・小児科・救急などが多い)で勤務することを前提に医学部6年間の学費の全額あるいは一部を負担してくれるというものです。
私立医学部の学費は非常に高額であるため、学費のサポートが得られる点で地域枠受験はメリットがあります。
地域枠受験のデメリット
しかし、地域枠で注意しなければいけないのは、条件があることです。
多くは下記のようになっています。
「大学卒業後、直ちに知事の定める医療機関で9年間勤務(臨床研修期間を含む)すること。(うち半分の期間は「医師不足地域の医療機関」での勤務)」
学費を負担してくれるのは相当魅力的ですが、医師の立場からすると、この条件は結構厳しいのが正直なところです。
多くの医師は医学生あるいは初期研修中に将来進みたい科や研修を受けたい病院、医局などを考えてゆっくり決めていきます。
しかし、この地域枠では医学生になる前からすでに科や勤務先病院を9年間も決められてしまうのです。(一応いくつかから選択する権利がありますが、相当少なくなります。)
卒後9年間といえば、初期研修、後期研修も終わっているので当然医局にも入っている時期ですから、そのような重要な選択の権利がかなり限られてしまうことになります。
実際に地域枠で医学部入学し、卒業した友人や後輩からは、あまり満足していないという声を聞いています。
これらのデメリットをしっかり考えた上で地域枠受験をするか検討するようにしてください。
地域枠の医師を採用した病院にペナルティがある
問題なのは、厚労省が地域枠で進学した医師への圧力を強くしようとしているということです。
実際、地域枠の医学生を採用した病院に対してペナルティを科しました。
地域枠は一定期間特定の地域で勤務すればよいという契約なので、地域枠の医学生にペナルティを直接科すことは出来ません。そこで、地域枠の医学生を採用した病院にペナルティを科しました。
ペナルティを負ってまで地域枠の医学生を採用する病院はまずないので、地域枠の医学生を受け入れる病院数が少なくなります。そのため、地域枠の医学生を採用する病院がなくなってしまったのです。
実質、このペナルティによって地域枠の医学生は間接的な勤務先の縛りを受けたことになります。
厚労省が地域枠の運用の厳格化を主張
また、2019年8月のニュースにて、厚労省が「地域枠で進学した医師は契約条件を満たした後も、道義的責任が残る。」と考えを示しています。すなわち、たとえ条件の9年間勤務を終了したとしても、道義的にその地域に残るべきだということです。
さらに、「医師偏在対策を進める上で地域枠の運用の厳格化が求められている。地域医療従事要件を果たさないと卒業できないなど、医師本人に対するペナルティも検討すべき。」と述べています。契約上、現時点では医師本人ではなく、地域枠の医学生を採用した病院にペナルティを科しています。しかし、今後は医師自身に対してもペナルティを科す可能性があるということです。
要するに、地域枠で医学部に進学した医学生あるいは医師に対してさらに厳格な対応をしていくと主張しています。
実際、地域枠で進学した医学生が親御さんの介護のために実家に戻りたくとも、契約条件を満たしていたにも関わらず指定された地域から離れられないという問題がありました。
増して、初期研修の研修病院先を選択するマッチングでは、地域枠の医学生は選択肢が別枠で設けられました。地域枠の学生は別枠の中から研修先を選択するため、マッチングの時点で制限をかけられたことになります。
これらの例から理解出来るように、地域枠の医学生をさらに制限していく発想になっています。地域枠で受験した医学生からすると、9年間働けば縛りがなくなる契約でしたが、契約条件を満たしても実質縛りから逃れられなくなってしまったのです。
新専門医制度とシーリング制度
最後に、新たに始まった新専門医制度とシーリング制度があります。
新専門医制度に変更されたことで、都心部以外で専門医を取るためには医局に入ることが必須になりました。そのため、多くの医師が都心部で研修することを希望し、東京での研修を希望する医師数が例年よりも3倍程度膨れ上がったのです。
そこでシーリング制度が新たに設けられ、都市部での専門医数を制限するようになりました。あらかじめ専門医数を制限することで都心部だけに研修医が集中することを防いだのです。
すると、都心部の病院でマッチング出来なかった研修医達が地域枠の学生の指定地域にある人気な病院から選択していきます。地域枠の医学生はそもそも別枠から研修先を選択しているため、希望者が多くなればなるほど、自己が希望する病院でマッチング出来る可能性は非常に低くなります。
これらの制度も地域枠の人にとっては少なくとも有利ではありません。


東京都枠について
さらに、東京都が行っている東京都枠という医学部受験もあります。
東京都枠については塾生にも多く相談されることですので、今回再度改めて都枠で入学した医学生および順天堂大学の医師にリサーチを行いました。
そのため、国公立医学部を志望する受験生は滑り止め感覚で都枠を受験することはできない。
まとめると下記になります。
東京都枠をおすすめできる人は、
・救急、小児科、産婦人科、僻地のいずれかに強い興味があり、今後希望科を変更しない自信がある。
・キャリアアップや自由に関心がなく、医師として勤務できればよい。
逆にそれ以外の方は、卒後9年間という縛りは医学部6年を含めトータル15年にもおよび、今後医療の需要も変わり、専門医制度などの変更もある状況で全く予想することができないためおすすめしないと考えられます。
最後に
上記で挙げたように、現時点でも地域枠の医学生に対する様々な制限が存在します。そして、制限が増えつつあることも事実です。そのため、今後地域枠の制限が現状よりもさらに厳しくなるリスクが十分にあります。
今回ご紹介したデメリットに十分注意した上で、地域枠受験を検討されると良いと思います。