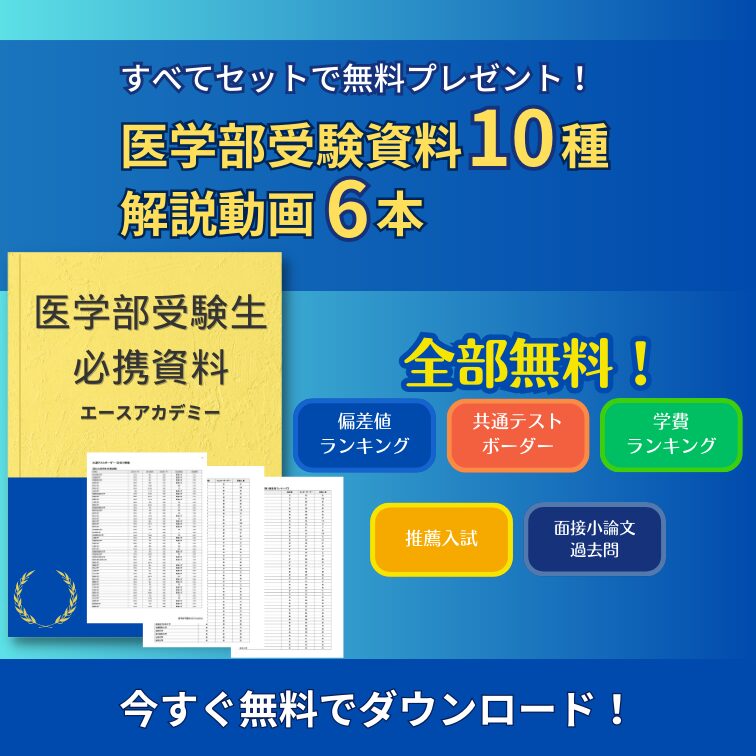<解説動画>
早い時期から志望校対策をする必要はない
高校の先生の中には、高3の6月くらいから志望校を決めて過去問演習をするよう指示される方もいらっしゃいます。
しかし、早い時期から志望校対策をするメリットはありません。
例えば、東京医科歯科大学を志望している受験生で、偏差値でいうと65ないくらいの人がいるとします。
模試で偏差値65が取れていない実力の場合、医科歯科大の過去問を解いても解けない問題が大半となっていまいます。
さらに、基礎力が不足している状態で応用問題集の解答を見ても得られるものは少なく、解きなおしをしたところで解答の丸暗記になってしまいます。
そもそも、高校3年生の6月というと、理科や数Ⅲの基礎を網羅的に習得できている人の方が珍しいです。
学習する順番として、まずは全教科全分野の基礎を抜けなく習得する方が優先順位が高くなります。
まだ基礎に抜けがある状態から志望校対策を始めてしまった結果、結局理科や数Ⅲの習得が間に合わず失敗してしまう例は少なくありません。
早い時期から過去問演習を行うのは、メリットがないどころか明確なデメリットがあるので注意しましょう。
志望校対策は合否に影響するか
医学部予備校で指導する中で徐々に分かってきたことではありますが、特別な志望校対策は医学部合格のために必須ではありません。
当塾では、受験が近づく秋ごろになると、基礎の習得が一通りできている受験生に対し過去問演習を指示していきます。
受験生の中には、多くの医学部を受験し受けた大学で複数合格される方もいますが、受験するすべての大学に対し、特化した対策をやりこんでいた訳ではありません。
わかりやすい例としては、現役生の生徒さんで複数の大学を受験し、時間の都合上過去問演習をできる大学が限られていた方がいました。
結果として国公立・慈恵医大・順天堂大を含む複数の大学に合格されましたが、慈恵医大の過去問は1度も行っていませんでした。
東京慈恵会医科大学は全教科難易度が高く、特徴的な出題もされますが、特化した対策は合格に必須ではないと言えます。
むしろ、実力がついていない場合、特化した対策をいくら行っても合格することはできません。
逆に、過去問演習をやりすぎたり、志望校に特化した対策に集中した結果生じてしまう失敗は多々あります。
例えば、「この大学ではこの分野がよく出題されている」といった場合、その分野に長い時間をかけて偏った対策をしてしまったとします。
しかし、その年度の入試でいきなり出題がなくなり、対策が手薄になっている分野がメインで出題されることがあります。
特に注意しておかなければならないのは、年度によって難易度や形式は変わることがある、という点です。
前年度までは難易度が低かったのに、急に傾向が変わり、難問メインの出題となるケースがあります。
こういった場合、過去問をやり込んで「○○大学の数学は簡単だから得点源にしないと!」と強く思い込んでいる受験生ほど危険です。想定通りに解けない時に冷静に対処することができず、半分パニックのような状態となってしまう恐れがあるからです。
難易度だけでなく、試験形式が急に変わることもあり、例えば英語で自由英作文がその年から課された、という事例もありました。
このように、試験本番は過去問通りにいくとは限りません。
「特別な対策」をやりすぎてしまうと、傾向が変わった時に柔軟に対応できずパニックになってしまう恐れがあります。
過去問演習は1-2年分行い、大まかな出題形式や傾向をつかんでおけば十分です。
学校や予備校が志望校対策を勧める訳
上記の通り、特別な志望校対策や、早い時期からの過去問演習は医学部合格のために必須ではありません。
しかし、学校や予備校では志望校対策を勧められることがあると思いますので、その点について解説します。
まずは学校の先生について。
学校の先生は、「過去に医学部に現役合格した人がやっていたこと」をそのまま勧めることが多いです。
医学部に現役合格する成績優秀な人は、早期から基礎が完成しており、早い時期から過去問演習を行っている場合があります。
しかし、早い時期から過去問演習を行ったから合格できたのではなく、早い段階で受験に対応できる基礎力がついていたから合格できた、と捉える方が正確です。
繰り返しになりますが、基礎力がついていない段階では、過去問演習よりも、全教科の基礎の習得が優先となります。
次に予備校についてです。
多くの予備校では、受験が近づくと「○○大学特別講座!」という大学別対策講座が開設されます。これは、大学別対策講座を行う明確なメリットがあるためです。
1つ目は、ビジネス的に利益がでるためです。
夏期講習などの短期講習と同じく、通年の授業料+αでの収益となります。複数の大学を受験する生徒さんの場合、受験校全ての大学別講座を申し込むとそれだけでかなりの金額となります。
2つ目は、受講生の実績を合格実績に反映することができるためです。夏期講習といった短期講座や、大学別対策講座の受講者も合格実績に入れている予備校は少なくありません。
(*受講生は別と明記されている予備校もあります)
夏期講習の記事でも記載した通り、直前の詰め込みで何とかなるほど医学部受験は甘くありません。
本当に志望校対策が特効薬のように有効なのであれば、志望校対策をやった人ほど合格に有利になるはずですが、特にそういった傾向はありません。
志望校の特別対策を受ければ合格できる、というわけではありません。まずは全教科で抜けなく実力をつけることを優先し、時間的に余裕がある場合に+αとして取り入れましょう、
まとめ
1年で医学部に合格する勉強法&おすすめ参考書
医師が執筆。医学部に合格するための勉強法・おすすめ参考書はこちら。