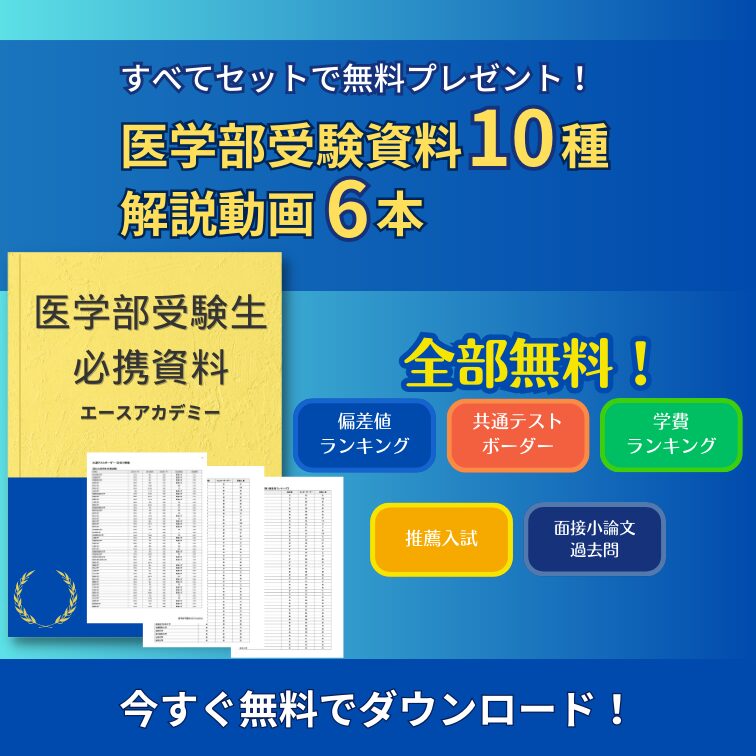体系物理の特徴
体系物理第6版には、複雑な数値の計算は無く、物理の本質的理解を深めるための創作問題で構成されています。また、物理法則を自分で導く「原理導出問題」が多く収録されています。
そのため、物理を本質的に理解するとともに物理的思考やセンスを身につけることができます。
本冊は各セクション、標準問題→発展問題で構成されており、回答は別冊で付録されています。
体系物理が医学部受験におすすめな理由
医学部受験参考書選ぶコツは、「科目間のバランスが取れるか」
医学部入試対策として、難問をすらすら解く力をイメージされる方は多いのですがそれは誤解です。
全教科で基礎を徹底的に身につけること、苦手科目・苦手分野といった抜けを作らないことが何よりも大切になります。
科目数が多く出題範囲も広い医学部入試において、科目間のバランスをとって勉強することは非常に重要であり、合否を分けるポイントです。
おすすめ理由① 網羅性を確保している
体系物理の問題数は、401問(基標準問題+発展問題)となっています。
標準問題のみでも、一定以上の網羅性を確保しているという特徴があります。
実際、発展問題を一切行わず、演習は体系物理の標準問題のみで医学部に合格した例は毎年多数出ています。
おすすめ理由② 自分が理解できていないところが分かりやすい
「物理に苦手意識がある」といった人の多くはそもそも公式が理解できていない、または解法を丸暗記してしまっている状態です。
体系物理はどの公式がその問題に適用できるか、それはなぜかを考えられるような問題が掲載されています。そのため、その場でわかったつもりになることを防ぎ、基本レベルの参考書に戻って本質を理解しようとする習慣が自然と身につきます。
*体系物理で分からない問題が多い人は、宇宙一分かりやすい物理シリーズを併用するのがおすすめです。
また、体系物理では面倒な数値計算がなく文字で一般化されているので、計算に時間をかけず、解法の習得に集中して取り組むことができます。
おすすめ理由③ 上滑りを起こしにくい
「物理の勉強をしているのに成績が伸びない」といった人の多くは上滑りを起こしています。
上滑りとは、基礎が十分に習得できていない状態で応用問題に取り組んでしまうことです。
物理は特に本質的な理解ができていないと、少しひねった問題になると全く手が出せないということになります。逆に言えば、ただ演習量を増やすだけでは対応できないということです。
体系物理では原理導出問題が多く載っているため、公式の本質を理解することができ、上滑りが起きにくいです。
医学部入試の物理の応用問題と呼ばれる問題の多くは、基本問題の複合問題に該当します。そのため、体系物理の標準問題で本質的な理解・関連付けができていれば、応用問題にも対応できるということです。
実際に使った感想(卒業生のレビュー)
もともと物理に苦手意識を持っていましたが、体系物理を使用して本質の理解をすることができました。
現役時代に使っていた問題集は解説に公式やポイントが丁寧に載っていることから、解説を読んで理解した気になっていました。解法を丸暗記してしまい、類題が出ても自力で問題が解けないことが多かったです。体系物理の解説は、解法は図でわかりやすく載っていますが、参考書のように詳しすぎません。そのため、解法を理解するだけでなく、自分はどこで詰まったのか(公式の理解不足か、パターンの整理ができていないのか、等)が見つけやすかったです。
また、計算量が少ないため、何周も繰り返すことで体系物理に載っている問題はすべて完璧にすることができました。
抜けなく学習することが大切な医学部入試において、1つの参考書を完璧にするというのは非常に大切だと思います。
1冊を完璧にするという面でも体系物理は使いやすく、物理以外にも勉強すべきことが多い医学部受験生におすすめの1冊です。